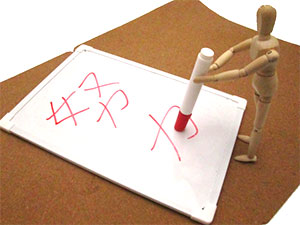欧州で最も経済的に厳しい国情であるうえ、個人で避難民を迎える家庭では費用がかさんでいるそうです(『東京新聞』(22年4月13日)。
こうした話を聞くと、世界的に見れば、まだまだ経済大国に入るはずの日本が、たった400人(4月19日時点では661人)程度の受け入れで胸を張っている場合なのでしょうか。
そのほかウクライナに隣接するポーランドには265万人、ルーマニア70万人、ハンガリー43万人、スロバキア32万人、ベラルーシ2万人、ロシア43万人が避難しているとか。人数ではポーランドが圧倒的に多いけれど、人口比だとモルドバが圧倒的に高い割合になるのだそう(同記事)。