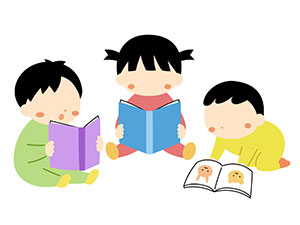たどり着いたのは、「周囲のおとなの違い」ではないかという結論でした。
たとえば、『希望と絶望の分岐点(1)』で書いた「英語教師になりたい」という少年の義兄は次のように話していました。
「(少年はアフガニスタンから逃げてきて)友達と離れて、ひとりで寂しそうだった。本人も手伝いたいと言うし、本人のためになると思ってここ(揚げパン屋)に連れて来た。本当は勉強させてあげて、大学へ行かせてやりたい。自分がやりたいことを選べる人生を送って欲しいから」
これを聞いて、「私だって、自分の子どもに対して同じように考えている」という日本人も多いのではないでしょうか。
日本人のおとなの多くは
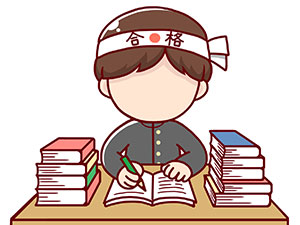
対して、日本のおとなの多くは、まず、おとなの側が選択肢を示します。
必ずしも言葉ではなくても、態度や自分の生き様、ちょっとしたため息などで「これか、あれか、それを選ぶべき」と、子どもに伝えています。
子どもが「学びたいことがあり、大学に行きたいから」ではなく、「大学を出ないと世の中で通用しない(と思い込んで)」子どもにお金や時間を注ぎ込み、それを愛情だと信じて、子どもに期待をかけます。
私は自分らしい人生を選択できているか
そして何より、日本のおとな自身が「こうでなければ」に囚われて生きています。自分の道を切り開いて行こうとするのではなく、日本社会が是とする道からはみ出さないよう、周囲を見て、自分が浮かないように生きています。
「自分が潰されてしまうくらいなら」と故郷を後にし、「自分の人生は自分で切り開いていける」と信じ、進んで行くアフガニスタンのおとなとはまるで違います。
希望と絶望の分岐点。それは自分を偽らず、自らの意思で、自分らしい人生を選択できているかどうかなのではないでしょうか。
はたして私はどうなのか。改めて考えさせられた番組でした。