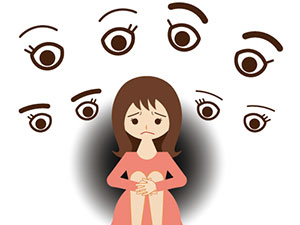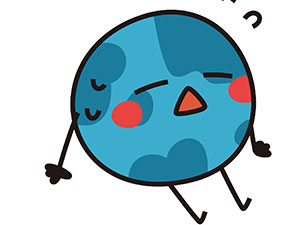同じ日の新聞の表と裏に、「希望と絶望」「理想と現実」「共生社会と競争社会」の縮図が載っているようで、なんとも言えない悲しい気持ちになりました。
皮肉と言えばいいのか、 シュールと言えばいいのか・・・。いまだにうまくこのときの気持ちを表現する言葉が見つかりません。
私も今の社会の一翼を担っている
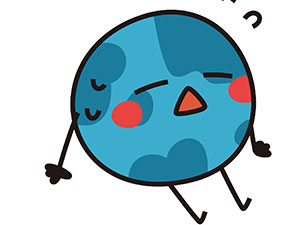
「
人と、動物と、自然すべてが、生き生きと輝く空間をつくりたい」という事業ビジョンを掲げる「もーもーガーデン」。
その取り組みには、 100%共感するし、心から応援します。「そんな世界ができたら、なんて素晴らしいのか!」と、その実現を願わずにいられません。
しかし、記事にあった非正規地方公務員の雇止めだけでなく、目先の利益にとらわれて人や動物や自然を破壊し、限られた者だけで利益を貪ろうとする大企業や日本政府。そんな社会の在り方を結果的に支えている、 国民がいるのも事実です。
私もその一翼を担っているのだと思うと、苦いものしかこみ上げてきません。
311後も何一つ変わらなかった
あの東日本大震災(311)を経験し、 あれだけの命と自然が犠牲になったのに。命ほど尊いものは無いと骨身に染みて実感したはずなのに。この国の政策も、選択も、ほとんど何一つ変わっていません。
それどころか、311以後の復興予算の使い方、コロナ対策の在り方、きな臭い世界情勢とこれらにともなう経済逼迫への対応を見ていると、いっそう「目先の利益優先」という風潮が強まっているように見えます。
エネルギー政策が典型例

よく分かるのが、エネルギー政策です。未曾有の人災に見舞われた福島第一原発事故後、いったんは原発依存を見直す雰囲気となり、その後の政権では原発の新増設や建て替えは「想定しない」としてきていました。
ところが昨年末、岸田文雄首相は、(1)次世代原発を開発・建設、(2)既存原発の60年超の運転を認める、という「GX(グリーントランスフォーメーション)」基本方針を決定し、原発回帰の姿勢を鮮明にしたのです。
「ロシアのウクライナ侵略で世界的なエネルギー危機が生じているから」と岸田政権は言います。
理念も信念も無い国の一条の光
一見、正論のように聞こえますが、つまりは「事情が変われば前提を覆すこともある」「窮すれば約束も保護にする」ということです。煎じ詰めれば、「政権運営者としての理念も信念もなく、行き当たりばったりに過ぎない」ということではないでしょうか。
そんな理念も信念も無い国に暮らしているからこそ、過酷な状況の中でもぶれない理想に向かって進もうとする「もーもーガーデン」に一条の光を感じるのかもしれません。