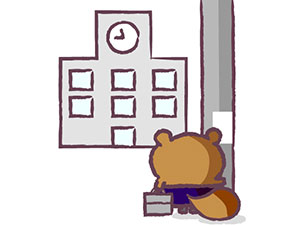「子どもの意見をきちんとすくうべき」
と言いながら、その意見の内容を政策等に反映する際は、
「子どもの年齢や発達段階、実現化に生、予算や人員なども考慮しつつ、子どもの最善の利益の観点で判断」
となっていて、
「意見がどう検討され反映されたか、反映されなかった理由を伝える」
と、同記事に書いてあったことです。
子どもの意見が大事だとか、子どもの声をすくうだとか言いながら、結局は、
「おとなが、おとな目線、おとな都合で判断し、決める」
ということに過ぎません。
子どもがどんなに一生懸命に考え、思いや願いを伝えても、それが「意味のあるものかどうか」を決め、「すくうかどうか」を決めるのはおとななのです。
おとなの自己満足かエクスキューズ
そんな権利の、いったいどこが「子どもの権利」だというのでしょう。そんな権利をわざわざ子どもに与えることにどんな意味があるというのでしょうか。
あえて意味を考えるとしたら「わたしはちゃんと子どもの意見も聴きましたよ」と、おとな側の自己満足を満たしたり、子どもに寄り添ったように見せるエクスキューズに過ぎないのではないでしょうか。
そんな子どもの権利はいらない!

だからこそ、「子ども」という存在なのです。
そんなおとなに及ばない子どもに、意見を言わせ、おとなの意に添えばそれをすくって「あなた(子ども)が決めたんでしょ!」と責任を子どもに負わせる。一方、意に添わなければ却下する。
そんな、おとながどうにでもできる、おとながいかようにも利用できる子どもの権利なんかいらない!