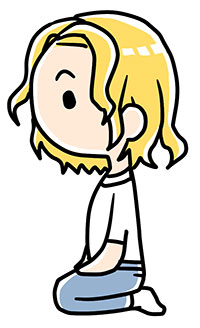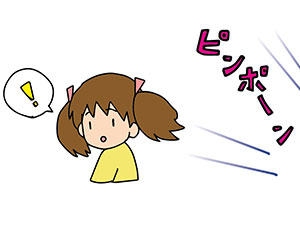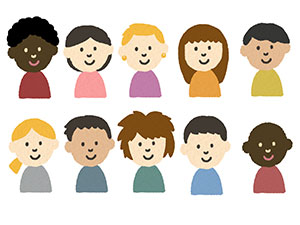ひとり黙々と課題をこなす毎日では、学べることは限られます。
“真の学び”とは、自らの力を伸ばし、その力を他者のために喜んで使えるよう、共感能力や好奇心を育てながら人格形成まで行うことです。
人格形成まで行う教育には、信頼関係や安心感が持てる他者との親密な関係が欠かせません。自分の成長を喜んでくれる仲間や、伸びた力を仲間のために使う経験、同じ場で、同じ空気を感じながら共に喜びを分かち合う一体感などが必要です。
どれもこれも画面越しのやりとり、オンラインでは得られないものです。
だから私たちの社会は、学校という教育機関をつくり、そこに信頼を置いてきました。学校が学習塾とは違う、ゆえんです。
とくにかわいそうな新入生

ところが、昨今は、「密を避ける」のがいいことと、対面授業もサークルもゼミもほぼ中止。新入生歓迎会や合宿などの行事も無くなり、せっかく大学に行っても「黙食の勧め」が各所に貼ってあり、「他者と接触するのは悪」というような空気感です。
なかには事務手続きや健康診断などで1~2回大学に足を運んだだけという学生もいます。
とくにかわいそうなのが去年の新入生でした。入学以来、一度も大学で授業を受けられていないという学生もいて、退学や休学に追い込まれるケースも見聞きしました。
自宅でたったひとり、ひたすら課題をこなすオンデマンド授業やライブ配信授業では、行き詰まりも感じます。地方出身者の中には、「オンライン授業なら実家に戻ろうと思ったが、親に周囲の目があるから帰ってくるなと言われた」という学生もいました。そんな状態で頑張って学べというのは酷というものです。
教育の原点の死滅
ワクチン接種が進み、コロナが収束した後はどうなるのでしょうか。「コロナ対策」として、各大学は遠隔授業のインフラ整備に多大なエネルギーと資金を投じました。
経済発展を望み、デジタルが大好きな政府も、そうした大学にたくさんの助成金をばらまきました。
いったん仕組みがつくられるとそれを止めることが難しいのは、コロナ禍で授業も満足に行えなかったのに実施された全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)を見ても分かります。
2007年、43年ぶりに全国学力テストが復活するとなった頃は、競争をあおり、教育格差を広げて、点数稼ぎのためだけの教育や不正行為が横行することなると警鐘を鳴らす声も多かったのに、最近ではもうほとんどそんな声は聞こえません。
いつの間にか「やるのが当たり前」になり、その問題点すら指摘されなくなってしまったのです。
“真の学び”に必要なもの
真に学び成長発達するためには、師として、友として安心し合える人間関係が不可欠です。一方的で無機質なオンデマンド授業を常態化させ、どんな教育で、どんな人間を育てようとしているのか。
コロナを口実に、教育の原点が死滅させられようとしています。