それからしばらくの間、私はその盲導犬の動きを観察していました。
なかなか電車が来なかったので、その間たっぷり15分はあったでしょうか。盲導犬は(当たり前のなのでしょうが)微動だにせず、ただジーッとユーザーさんの足下でうずくまっていました。
満杯の電車を見送り、次の電車に乗るつもりなのでしょう。ユーザーさんはようやく到着した電車には乗ろうとしませんでした。
そんな二人(一人と一頭?)の横をすり抜け、電車に乗り込むと、ちょうどホームで待っている盲導犬と窓ガラスを挟んで真っ正面に向き合うような格好になりました。
ホームに停車したままの電車から、盲導犬に「お疲れ様」とアイコンタクトでメッセージを送ろうとしたときのことです。うつむいて寝そべっていた盲導犬が、ふいに面を上げました。

 だって、あれだけ毎日毎日、たくさんの時間を共に過ごしてきた犬です。おしっこやうんちの世話をし、変な物を食べてお腹をこわしたときには添い寝をし、雨の日も風の日も散歩をして、一緒に歩んできた犬です。
だって、あれだけ毎日毎日、たくさんの時間を共に過ごしてきた犬です。おしっこやうんちの世話をし、変な物を食べてお腹をこわしたときには添い寝をし、雨の日も風の日も散歩をして、一緒に歩んできた犬です。 これは本当にすごいことです!
これは本当にすごいことです!
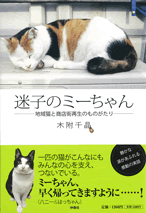 この相談室のブログに書いていた「
この相談室のブログに書いていた「