 「家族のなかみ」こそ大切
「家族のなかみ」こそ大切
このように言うと、「夫婦別姓や事実婚を認めたら家族が崩壊する」と、反論する人たちがいます。
婚姻制度という“ちょうつがい”を外したら、夫婦も家族もバラバラになってしまうから、そんなことはとうてい許すことができないというわけです。
でも、そんな家族(夫婦)は、すでに家族としての機能ーー愛情や共感、温かさや尊敬、安心や自由などをお互いに与え合うことーーを失っています。
そのいちばん大切な部分を無くし、バラバラになった人々を無理やり家族という器に押し込めようとすれば、かならずどこかに歪み=病理が生じます。




 「フィリピン ベッドタイム ストーリーズ」という芝居を観ました。フィリピンの演劇人と交流を重ねてきた日本の劇団・燐光群が両国スタッフ共同で創り上げた作品です。
「フィリピン ベッドタイム ストーリーズ」という芝居を観ました。フィリピンの演劇人と交流を重ねてきた日本の劇団・燐光群が両国スタッフ共同で創り上げた作品です。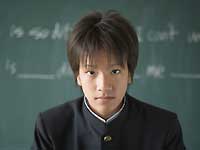 それでなくても子どもが本音を語ることは容易ではありません。そのことを教えてくれたのは、以前、このブログでご紹介した「子どもの声を国連に届ける会」のHさんです。
それでなくても子どもが本音を語ることは容易ではありません。そのことを教えてくれたのは、以前、このブログでご紹介した「子どもの声を国連に届ける会」のHさんです。