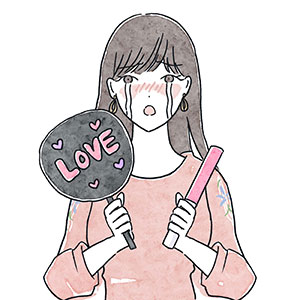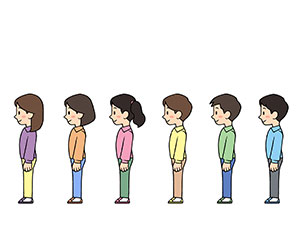
「8時15分から25分の10分間に教室に入れるよう登校しなければならいというルールがあるんです。もし、それより早く登校した場合は昇降口で学年ごとに、校帽をかぶったまま整然と並んで待つのが決まり。校庭で遊んでも、教室に入ってもダメ」
絶句する私をよそに、他の人から「家の近所の学校も!」という声がいくつも上がりました。
まるで軍事訓練です。いったいなぜ? ある保護者はこう推測します。
「たぶん、安全の問題だと思います。まだ先生たちも教室にいないし、目の行き届かないところで何かあれば困るから、『おとなしくじーっとしていて欲しい』ということなのではないでしょうか」
またもやおとなの都合優先! こうやって子どもの欲求を潰していくのです。
子どもらしさを削がれた子ども
カウンセリングの場でも、「登下校中の子どもの問題行動」として、「一列に並べない」とか「興味があるものがあると立ち止まる」とか、「友達と大声ではしゃぐ」などがあがることがあります。
そのいったい何がいけないのか? 首をかしげるばかりです。子どもは道草をくったり、興味のあるものに惹かれたり、はしゃいだりするものです。それが「子どもらしさ」です。興味関心が子どもの好奇心を育て、生きる力につながります。
うちの近所でも登校時の私語が禁じられているのか、無言で静々と並んで歩く小学生を見かけます。まるで葬式の参列のようで、いつも心配になります。
黙って従う国民づくりのリハーサル

実は校則の存在は、私にとって長い間、謎でした。
小中高を通して、「どうしてスカートの丈は膝下10センチでないといけないのか」「なぜ、肩についた髪は結わかないといけないのか」「鉛筆はよくてシャープペンシルはダメなのか」・・・。学校には謎のルールがたくさんありました。
教師に尋ねても「決まりだから」と言われるだけ。食い下がると、「面倒な子ども」という顔をされました。いつも判然としない、もやっとした思いを抱えながら、なんとなく過ごしていました。
でも、もしそれが「黙って従う国民(良民)づくりのリハーサル」だと言われれば、「なるほど、それは有効だ! と思えます。