なぜならそもそも少年法は、生育環境などの問題でうまく成長・発達することができなかったため、反社会的な行為をしてしまった未成年者が生き直せるよう、健全育成と環境調整を行うための法律です。
だから、少年法では教育・保護し更正することに力点が置かれています。
男性は、こうした少年法に基づいて医療少年院で約7年の治療を受け、社会へと復帰しました。
被害者や被害者遺族を誹謗中傷するような、もしくは犯した罪を肯定したりするような本なら批判されてもしかるべきでしょう。しかし、ただ「自分の気持ちを語りたい」と手記を著すことがなぜいけないのでしょうか。
少年法の考えに則れば、匿名での執筆も当たり前の話です。死刑が確定していた永山死刑囚とは違い、男性はこれからもこの社会の中で生きていかなければならないのです。本を出版しただけで、これだけの騒ぎが起きる日本社会ですから、顔と名前が周知されればどんなことになってしまうか・・・。火を見るよりも明らかです。
日本は閉塞的で不自由な社会
平気で男性をバッシングし、書店や図書館が「本を扱わない」という自主規制に走る日本社会は、少年法の精神をまったく理解していないだけでなく「罪を犯した者は一生口をつぐみ、『ごめんなさい』と小さくなって生きるべきだ」という閉塞的で自由がない社会でもあります。
こうした社会では、人々は逸脱行為をした者に「自分とは違う理解不能のモンスター」という烙印を押し、切り捨て、つぶしていきます。
それによって被害者らが何よりも知りたい「なぜ、自分の大切な人がこんな理不尽な被害に遭わなければならなかったのか」という問いの答えは永遠に闇に葬られます。だって犯行に至る経緯や生い立ちも見えなくなってしまうのですから。
真に安全な社会を築くには
犯罪に至る原因やきっかけが分析できなければ、何が犯罪の引き金になるのかも、逆に何が抑止力になるのかもわかりません。結果として社会は大きなリスクを負い、「犯罪の凶悪化」という負のスパイラルに陥っていきます。
だれもが安心して暮らせる安全な社会を築く最も確かな方法は犯罪者を厳罰に処することではありません。
犯罪者の人生を紐解き、何が犯罪に向かわせたのかを明らかにし、社会の中から同様の犯罪要因を取り除き、環境に恵まれなかった子どもをなるべく早い時期から支援していくことです。

 労働者の祭典であるメーデー(5月1日)や憲法記念日(5月3日)などがあったつい先日のゴールデンウィーク期間、個人的な都合で奇しくもさまざまな法律を学び直す機会がありました。
労働者の祭典であるメーデー(5月1日)や憲法記念日(5月3日)などがあったつい先日のゴールデンウィーク期間、個人的な都合で奇しくもさまざまな法律を学び直す機会がありました。 確かに10年くらい前から日本はとても多くの自然災害に見舞われています。以前なら「震度4」と聞けば「かなり強い地震」という印象を持ちましたが、最近では「震度5」のニュースを聞いても驚かなくなってしまいました。
確かに10年くらい前から日本はとても多くの自然災害に見舞われています。以前なら「震度4」と聞けば「かなり強い地震」という印象を持ちましたが、最近では「震度5」のニュースを聞いても驚かなくなってしまいました。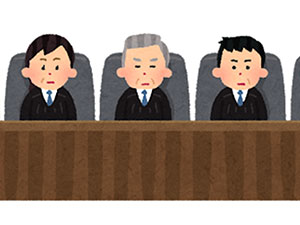 同制度を使うメリットとしては、「集中審理が行われるので審理期間が短縮される」「裁判が身近で分かりやすいものになる」「司法への信頼の向上につながる」などが喧伝されました。
同制度を使うメリットとしては、「集中審理が行われるので審理期間が短縮される」「裁判が身近で分かりやすいものになる」「司法への信頼の向上につながる」などが喧伝されました。 少年法は、家庭環境に恵まれないなど、さまざまな事情でうまく成長・発達することができなかった少年の生き直しを目的につくられた法律です。そのため、罰を与えるのではなく、教育や保護を行って更正を促すことに力点が置かれてきました。
少年法は、家庭環境に恵まれないなど、さまざまな事情でうまく成長・発達することができなかった少年の生き直しを目的につくられた法律です。そのため、罰を与えるのではなく、教育や保護を行って更正を促すことに力点が置かれてきました。 罪を犯すところまで追い詰められた少年の生い立ちが軽んじられるようになる一方、犯罪被害者等基本法制定後の2008年にはじまった被害者参加制度によって、裁判員は被害者やその家族から直接、辛さや苦しみを聞かされることになりました。
罪を犯すところまで追い詰められた少年の生い立ちが軽んじられるようになる一方、犯罪被害者等基本法制定後の2008年にはじまった被害者参加制度によって、裁判員は被害者やその家族から直接、辛さや苦しみを聞かされることになりました。
 厳罰化の一途をたどっている少年法。こうした流れをつくったのは、2006年に山口県光市で起きた母子殺害事件でした。
厳罰化の一途をたどっている少年法。こうした流れをつくったのは、2006年に山口県光市で起きた母子殺害事件でした。 そんな障害者差別について深く考えさせられたのは、昨年7月26日に放送されたNHKのクローズアップ現代を見たときでした。
そんな障害者差別について深く考えさせられたのは、昨年7月26日に放送されたNHKのクローズアップ現代を見たときでした。