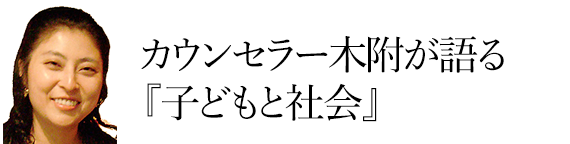日本人の法感覚(5)
裁判員制度の導入に向かっていた当時、司法に関わる者の研修に関しても気になる話を耳にしました。
取材を受けてくれた調査官は「非行につながる環境要因等は簡略化し、『刑事処分相当』との意見を『要にして簡潔に』記すよう求められた」と研修について語りました。
また、調査官や裁判官・検察官・弁護士の研修を行う最高裁判所司法研修所は「これまで重視されてきた成育歴や素質などの調査記録を証拠とせず、主に法廷での少年の供述内容で判断した方が望ましい」との研究結果をまとめていました。
加害者の生い立ちが見えなくなる一方
 罪を犯すところまで追い詰められた少年の生い立ちが軽んじられるようになる一方、犯罪被害者等基本法制定後の2008年にはじまった被害者参加制度によって、裁判員は被害者やその家族から直接、辛さや苦しみを聞かされることになりました。
罪を犯すところまで追い詰められた少年の生い立ちが軽んじられるようになる一方、犯罪被害者等基本法制定後の2008年にはじまった被害者参加制度によって、裁判員は被害者やその家族から直接、辛さや苦しみを聞かされることになりました。
もし我が子を殺された家族であれば、当然、死んでいった子どものへの思いや、子どもの無念さ、自分たちの未来や希望がどれほどずたずたに引き裂かれたかなどを涙ながらに語るでしょう。私が被害者家族であっても、きっとそうすると思います。
被告人である少年の「なぜ犯行に至ったのか」が見えなくなるなか、被害者側の苦痛を目の当たりにすることになった裁判員の心に「被告人を許せない」という感情が沸いても不思議ではありません。
「国民の常識」と呼べるのか?
評決の際には、「素人である裁判員が参考にできるように」と、裁判官が類似の事件でどんな判決が下されたか(量刑相場)を示すこともあるでしょう。
いえ、たとえそのようなものが無くても、被告人の個人的な事情がわからなければ、犯行行為以外に判断材料はありません。「○人殺せば死刑」「致死なら無期懲役」など、パターン化した結果にならざるを得ません。
こうしたなかで下される判決が、果たして「市民感覚」が生きた「国民の常識」と呼べるものと言えるのでしょうか。
被害者側も救わない
こうした裁判は被害者側も救いません。前出の調査官は、大勢の被害者と接してきた経験からこんな話をしてくれました。
「被害者や遺族が知りたいのは、『なぜ大切な人がそんな目に遭わなければいけなかったのか』です。それに応えるためには、被告人がどんなふうに育ったどんな人間なのか、なぜ犯行に及んだのか、などが明らかにならなければいけない。公判前整理手続でそこが削られてしまえば、被害者側の傷はもっと深くなります」