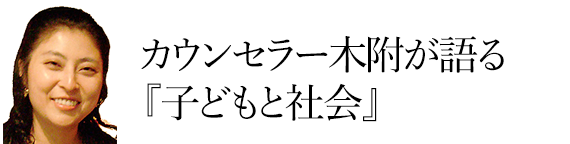地下鉄サリン事件から30年の「もやっ」とした話

『東京新聞』(25年3月14日)では、サリン事件の実行犯役のひとりで無期懲役が確定している杉本繁郎受刑者が同紙に寄せたという手記も。こんな紹介でした。
「(杉本受刑者は)事件について『最終解脱者は何をやっても(略)すべて許されるという妄想を本気で信じ込んでいた麻原影晃(本名・松本智津夫元死刑囚、2018年7月死刑執行)の妄想の集大成、それが地下鉄サリン事件だった』と総括。社会へのカルトの浸食があらためて不安視される現在、『生の続く限り、知っていることのすべてを語り続けたい』としている」
あさましい権力者たち
一連の「オウム真理教事件」を検証すること自体は否定しません。しかし、宗教という、多くの日本人がアレルギー反応を感じる“特殊な”ものに矮小化されてしまうのは、ちょっと「もやっ」とします。
「最終解脱者は何をやっても(略)すべて許されるという妄想」の「最終解脱者」の部分を「巨万の富を持つ者」と置き換えたら、アメリカに象徴される、現代社会の権力者となんら変わりありません。
金と権力を背景に「自分は特別」という妄想にとらわれ、平気で他国の領土を侵略し、資源を横取りし、自国(自分)の利益だけを追求する。権力者たちのほうがもっとあさましい気さえもします。
私の人生を変えたオウム真理教事件

思えば、今の私があるのは同事件があったからです。
サティアンと呼ばれるオウム真理教の施設(山梨県旧上九一色村)から、必死で抵抗するオウム真理教信者の子どもたちが、機動隊や警察官に力づくで、次々と担ぎ出され、それを「またひとり、子どもが“保護”されました!」と実況中継する報道陣。
その姿に、大きな大きな「もやっ」と感を覚えたことが、子どもの権利条約に惹かれる要因をつくり、マスコミの世界から心理の世界へと転身するきっかけになりました。
そんな私の人生を変えた事件から、はや30年。そして去年は日本が子どもの権利条約を批准して30年でした。
そんな節目に、もう一度、子どもの権利のことを考えて行きたいと改めて思う、今日この頃です。