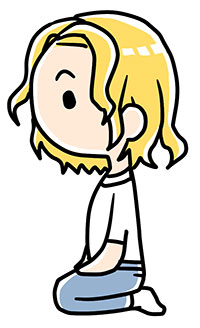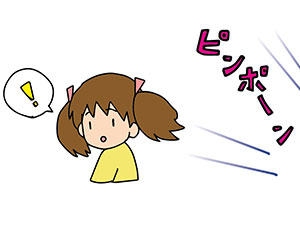5月5日は「子どもの日」でした。
例年に漏れず、昨日は子どもの日にちなんだ全国各地のイベントや、「子どもの数の減少」(前年より35万人減)、「不登校」(23年度の小中学校の不登校数は34万6482人で連続11年増加)など、子どもに関するニュースがさまざま報道されました。
そうしたなか、またもや「もやっ」とした記事が・・・。
「子どもの意見 すくえていますか?」(『東京新聞』5月5日)という見出しが躍る、子どもの権利、とくに昨今「最も大切!」と声高に叫ばれている子どもの意見表明に関する記事です。
『東京新聞』の記事

同記事は、2023年4月に施行された「子ども基本法」を子どもの権利を総合的に保障し、子どもの意見表明権を盛り込んだと書いています。
東京都が行った子どものヒアリングや、都がヒアリング(子どもの意見聴取事業)を受託した団体のコメントが紹介され、「言語化できない子の思いも引き出してもらえた」(子ども条例の制定を目指す東京都狛江市の担当係長)という手ごたえも載っていました。
都は、「子どもの声を『翻訳』し、行政とつなぐ役割の重要性を感じている」と、聴き手となるおとなのスキルアップのため、実践事例集も公表するほどの力の入れようです。
都や国が考える「子どもの権利」とは?
しかし、記事を何度読み返しても、都や国が子どもの権利をどのようにとらえているのかが分かりません。
こども家庭庁のホームページには、「こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としている」とあり、こども基本法第三条の6つの基本理念(以下)も紹介されています。
一 個人として尊重され、基本的人権が保障され、差別されない。
二 適切に養育され、生活を保障され、愛され保護され、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られ、福祉に係る権利と教育を受ける権利が等しく保障される。
三 年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保される。
四 その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先される。
五 こどもの養育は、家庭を基本として行われ、保護者が第一義的責任を有し、そのための十分な支援を行い、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保する。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備する。
子どもの権利条約のどんな精神にのっとっている?
子どもの権利条約の画期的なところは、従来の権利の考え方では権利主体とはなり得ないはずの子どもが使える(権利行使の主体となりえる)点です。それが世界的、国際的な約束事になったのですから、本当にすごいことです。
ところが、こども家庭庁のホームページを見ても、こども基本法を見ても、そうは読めません。子どもの権利条約のどんな精神にのっとっているのかも分かりません。
子ども自身が使えないのが「子どもの権利」?
個人として尊重されること、適切に養育されること、社会に参画すること、家庭(保護者)によって養育されること・・・。それらが保障されることが大事なのは同感です。家庭や子育てに喜びを持てる社会をつくることも大賛成です。
しかし、このように並べ立てても、子どもが、子ども自身で実現できるものなどひとつもありません。このままでは、ただ養育(教育)に関わるおとなの義務や道徳、社会のあるべき姿が網羅されているだけです。
これでは子どもは相変わらず、「おとなに庇護される客体であって、権利行使主体ではない」ことになります。
子ども自身が使えないのに、それが子どもにとって大事な「子どもの権利」なのでしょうか。