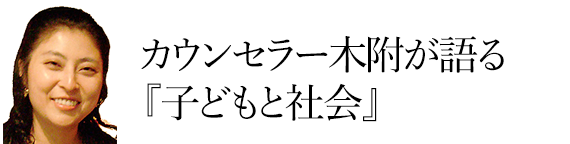暴力的な社会(7/7)
逆に、一見、正義のように見える加害者を死刑などの厳罰に処すこと。
すなわち、加害者だけに責任を負わせ、犯行の背景を一切語れぬように「口をぬぐう」こと。
加害者が「なぜ犯行に至ったか」を注視せず、「やったこと」のみに焦点を当てること。
加害者が犯行に至るまでの間、加害者を救う努力をしてこなかった社会の責任を放棄すること。
それは、加害者のような人間を生み出した社会・環境の問題を温存させるだけでなく、多くの人々を憎しみと恨みの中に定着させ、さらなる破壊的な社会へと人々を邁進させる暴力の連鎖を強めることになります。
最高裁の罪深さ
こうして改めて考えると、最高裁が光市母子殺人事件の判決で「とくに酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかない」と、犯行時18歳であっても「原則として死刑適用」という新たな判断の枠組み示したことが、いかに罪深いことであるのかが分かります。
“最後の正義の砦”たるべき最高裁が、憎しみと恨み渦巻く暴力的な社会を後押ししてしまったのです。国の価値観を決定する最高裁が、社会の責任を放棄し、すべてを個人の責任に決着させて良いと判断したのです。
そして結果的に、暴力的な社会が変換する機会を潰してしまったのです。
罰されるべきは社会
まだまだ書きたいことはありますが、今回はひとまず非行(犯罪)と子ども、そして社会との関連について鋭い指摘をした2人の賢人の言葉を借りて、終わりにしたいと思います。
臨床心理学修士であり、アメリカのカリフォルニアで心理療法に当たっているジェーン・スウィガードは著書『バッド・マザーの神話』(誠信書房/309ページ)で、こう言っています。
「私たち(おとな)の行動が真に破壊的になると、子どもたちはギョッとするような悲劇的なやり方で警告してくれます。ティーンエイジャーの自殺やうつ病、暴力事件の増加や学校における不幸な薬物の蔓延などで、このような現象は低年齢化し、今や思春期前の子どもの間にまで広がっていきます。子どもたちの行動の意味するところや子育ての心理的現実を探ることによって、私たちの止める時代が抱える病弊のより深い意味を理解することができるのです」(下線部は筆者が加筆)
そして、イギリスの哲学者で経済学者でもあるジョン・スチュワート・ミルは、すでに1800年代にかの有名な『自由論』で、こう指摘しています。
「社会が子育てに失敗し、非行者を生み出してしまうとするなら、そのことについて責められるべきは社会自身である」
賢人達の声に耳を貸さず、厳罰化を進めることは、実は私たち自身さえも脅かす、今よりももっと暴力的な社会をつくることにつながるのです。