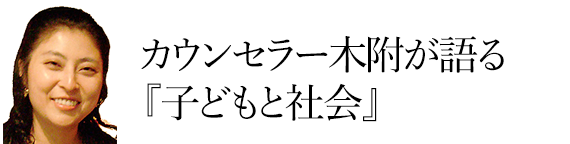生い立ちと人格(3/5)
なぜなら子どもというものは親の非常な仕打ちを忘却し、そんなひどいことをする親を理想化しなければ生き延びることはできないからです。
親が“親の都合で”子どもを苦しめているとか、子どもが親の葛藤やストレスをぶつける対象になっているなどという考え方は、子どもにはできません。愛する親が、「自分のことを愛していない」ことを受け入れることほど、子どもにとって残酷なことはありません。
だから子どもは「親が怒るのは自分が悪い子だからだ」とか「自分のためを思って親は自分に厳しく接するのだ」と、親の仕打ちを合理化せざるを得ないのです。
激しい暴力にさらされていたヒトラー
ヒトラーに話を戻しましょう。
ミラー氏は、数多くのヒトラーに関する研究や伝記から、ヒトラーは3歳くらいの幼い頃からほぼ毎日、父親にむち打たれるという激しい暴力にさらされ、その名前も呼んでもらえず、犬のように指笛で呼びつけられる、「何の権利も認められぬ名無しの存在」(同書210ページ)であったと記し、それはヒトラー台頭時のユダヤ人の身分とそっくりだと言います。
でも子どもだったヒトラーは、こうした屈辱や恐怖心をすべて押さえ込み、感じ無いようにすることで日々乗り越えるしかなかったのです。母親は、心配はしてくれても彼をかばうだけの勇気も力も無かったからです。
たとえばミラー氏は伝記作家の次のような文章を引用しています。
「それで私(ヒトラー)はその次殴られることがあったら、絶対声を出したりしないぞと決心したのだよ。実際にそういうことになった時ーーまだはっきり覚えているがね、母が部屋の外に立って心配そうにドアからのぞいていたよーー私は一打ちごとに父と一緒になって数えたものだ。私が誇りで顔を輝かせながら『お父さんは僕を32回もお打ちになったよ!』と知らせに行った時、母は私の頭がおかしくなったと思ったものだ」(同書204ページ)
憎しみが権力を握ったとき
こうやって幼きヒトラーの中に誕生した憎しみは、ヒトラー自身も知らないうちに成長していきました。
表出されられない痛みや、自分を傷つけ、辱める者を愛さねばならないという現実を栄養源に、憎しみはどんどん増幅していったのです。
そしてその憎しみが権力を握ったとき、それは生あるすべてを破壊する力となって、何百万という人々を苦しみと恐怖の中に投げこむことになりました。(続く…)