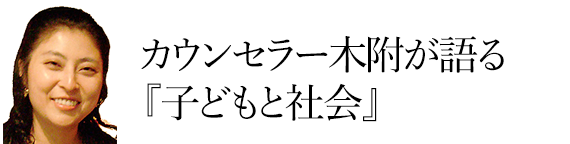「生命力の種」ーー新年のあいさつに代えて(3/4)
私が取材で会った子どもの中には、この「一時保護」そのものが、トラウマになっている場合もめずらしくありませんでした。
「人見知りをしなかった子どもが、男性を怖がるようになった」
「ひとりで留守番させようようとすると『警察が連れに来るかも知れない』とおびえる」
・・・そんな声も聞かれました。
はじめて知った「心理職」の仕事
こうした体験をした子どもが、警察や社会に対して、否定的な印象を持つことは意外でもなんでもありません。
むしろ、「当然」と言っていいことでしょう。
ところが、「保護」された子どもを担当したある「心理職」の方は、子どもの母親に対して親元に返せない理由をこんなふうに語ったそうです。
「心理検査したが、まだマインドコントロールが解けていない。しかも、『警察は嫌いだ』などと、反社会的なことを言っている」
でも、いったいどんな心理検査が行われたのか。どんな基準で判断しているのか。何より、なぜ子どもたちが「反社会的なことを言うようになっているのか」については、まったく触れられませんでした。
これが、私がはじめて知った「心理職」の仕事ぶりでしたから、私が「心理という仕事」に対して、批判的かつ懐疑的だったのはあたりまえでしょう。
心理を学ぶに至る経緯
話をうんと最初のところに戻しましょう。
この一件があってからというもの、心理職に対してまったくいい印象を持てずにいた私をよそに、世の中には「こころブーム」が到来しました。
スピリチュアルなものから専門的なものまで、娯楽雑誌から教育現場まで、あらゆるところに「こころ」というキーワードが氾濫し、「こころの時代」などと呼ばれるようにもなりました。
実は、この背景にもさまざまな仕掛けがあるのですが、それもまた長くなるので別の機会に譲っておきましょう。
とにかく、あっちでもこっちでも「こころ」をめぐる現象がさまざま起き、それまで振り向きもされなかった心理の専門家は、「まるでこころを自由に操れる魔法使い」のごとく、珍重されるようになりました。
国家権力におもねる心理の専門家や、そんな心理の専門家を利用しようとする権力者が目に付くようになり、「こうした人々をきちんと批判した記事を書くためには、自分が心理に詳しくならなければ」という思いが私の中で強くなっていき、やがて心理の大学院へと進む決心をしました。
このオウム事件の数年後に、以前「真夏の怪(3)」で書いた「子どもの心をおとな(社会)に合わせてつくり変える」ためのツールである『心のノート』が、高名な心理学者を中心につくられたことも、その決心を後押ししました
でも、そのときはまさか自分が心理臨床を仕事とする人になるとは、予想だにしていませんでした。(続く…)