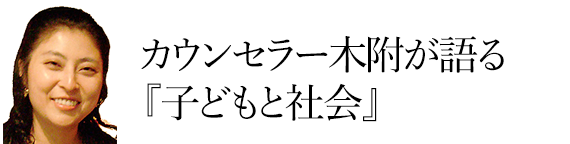さとり世代(9/10)
「怒り」を安心して表現できる環境が保障され、関係性の維持を求める欲求に応じてくれる養育者に出会うことができれば、乳幼児の「怒り」(泣き叫び)は、少しずつ洗練されていきます。
その子の発達度合いに応じて、ただ泣き叫ぶのではなく、身振りや手振り、言葉や意見など、もっと有効な方法で自分のニーズを表すようになっていき、やがて意見表明や自己主張と呼ばれるものへと変わっていきます。
一方、不運にも安全な環境や求めに応じてくれる養育者に恵まれなかった場合、子どもは「怒り」という、他者に助けを求めるサインを適切に表すことができなくなってしまいます。「求めても他者は応じてくれない」と学習し、他者の助け、他者との関係を求めることをやめてしまうのです。
スピッツの調査報告
1945年、児童精神科医のスピッツがまとめた、有名で、かつとても興味深い乳児についての調査報告があります。
母親から引き離された乳児は、最初はさかんに泣きますが、そのうち泣かなくなり、無表情・無反応になっていくというものです(Spitz,R.A.(1945):Hospitalism.An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood.Psychoanalytic Study of the Child,1,53ー74.)。
さらにスピッツは、その後も母(養育者)によるケアがなかった場合、乳児はホスピタリズムと呼ばれる情緒的発達および身体的発達の障害を来し、死に至ることもあるとも述べています。
ボウルビィの「悲哀の過程」
また、第二次大戦後の戦災孤児の調査や、乳幼児と親の関係を研究した愛着理論の立役者・ボウルビィは、大切な愛着対象を失ってから、新たな愛着対象との創造的な関係を結ぶに至る心的過程を次のように考えました。
(1)失った事実を認められない段階、(2)失った対象を探し続け、あきらめきれずに強い怒りを感じる段階、(3)対象が戻って来ないとあきらめ、絶望する段階、(4)新たな愛着対象との関係性を結び始める段階。
でも、新たな愛着対象が見つからなかったらどうでしょうか。「求めても仕方がない」とあきらめ、無気力になってしまうのではないでしょうか。(続く…)