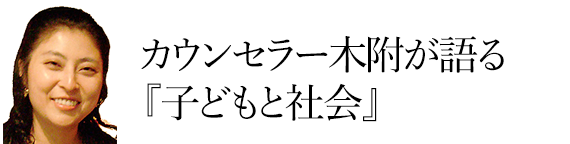感情はもううざいし要いらない(4/8)
 動き出す電車の中で遠くなっていく盲導犬を見つめながら記憶のページをめくっていくと・・・と思い当たった顔がありました。
動き出す電車の中で遠くなっていく盲導犬を見つめながら記憶のページをめくっていくと・・・と思い当たった顔がありました。
児童養護施設の子どもたちのインタビュー集(『子どもが語る施設の暮らし2』明石書店)をつくったときに出会ったある中学生の男の子でした。
「今の生活をどう思う?」
「何かおとなに言いたいことある?」
「不満に思っていることは?」
いろいろと尋ねても、その子はただ「べつに」という回答を繰り返すだけ。私と目を合わせようともしませんでした。
それでも質問を重ねていくと、その子はうんざりしたようにため息をつき、こう言ったのです。
===
「不満を言ったら何か変わるんですか? 何かしてくれるんですか?」
そのときの男の子の瞳。何も見ていない、何も感じていない、何も考えようとしない瞳・・・。
それはさっき出会った盲導犬に似ていたように思えました。
「欲求や感情をすべて封じ込め、「自分」というものを出さず、与えられたもの(役目)だけを受け止めている」
そんな雰囲気の漂う瞳の色でした。
誤解のないように
誤解のないよう述べておきたいのですが、盲導犬の役割や存在を否定するつもりはまったくありません。
しかし、前にも書いたようにわが家のやんちゃ娘(愛犬)や、テレビで見たパピーウォーカーと暮らしているときの盲導犬候補犬の生き生きとした表情と、ホームで出会った盲導犬の表情があまりにも違うことが不可思議でした。
あの好奇心がいっぱい詰まった欲求の塊のような子犬が、どんなふうに成長したらこんなにも周囲に影響されず、自分から関心を示さず、ひたすらユーザーさんに忠実な犬になるのかというのが気にかかったのです。
もっと言えば、「育ち方によっては人間にも同じことが起きるのだろか?」という疑問が、そこにはありました。(続く…)