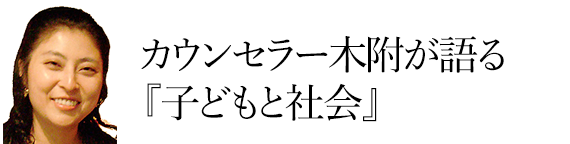野田市小学4年生虐待死事件について考える(4)

ひとつは、「虐待をするような親は自分とはかけ離れたモンスター」と考えるのを止め、「だれもが虐待者になり得る」という現実を受け入れることではないでしょうか。
そのうえで、過去に起きた虐待事件の加害者の生い立ちをできるだけ多く、そして徹底的に明らかにすることが必要です。
前にも書いたように、「虐待の連鎖」という視点から考えれば、加害者はかつて被害者だったはずです。
彼・彼女らの人生がどんなもので、どんな家庭で、どんな人間関係のなかで生きてきたのか。どんな思いを抱えて成長し、どんな経緯で親となったのか。
それが分かれば、何が暴力の引き金になり、逆に何が抑止力になり得たのかや、虐待者になる、ならないという分岐点がどこにあったのかも分かるはずです。
「親は子どもを愛する」との神話からの脱却
ふたつめは、「親は子どもを愛するもの」という神話、とくに「母性本能」という考えを捨てることです。
今回の事件でも、父親の暴力を止めるようとしなかった母親への批判が相次いでいますが、そこには、「女性として生まれたからには「母性本能」が備わっており、子どもを慈しんで育て、子どもを守るためならすべてを投げ出すものだ」という考えが見て取れます。
しかし、事情はさまざまあれ、暴君の前で女性が我が子を守れないことは多々あります。それどころか自身の保身に走り、子どもを差し出すことだってあり得るのです。
ストレス耐性にも親との関係が影響
子どもを育てるということは本当に大変です。身勝手で、後先考えず、自己主張ばかりして、親の時間とエネルギーを一方的に奪う子どもを「かわいい」と思うには、精神的にも経済的にも、ある程度の余裕が必要です。
「虐待の連鎖」の発生率を予測した研究では、被虐待者が虐待を行う確率は3分の1ほどですが、精神的ストレスが高まると虐待者になりうる者が3分の1いると言われています(『いやされない傷 児童虐待と傷ついていく脳』友田明美・診断と治療社 7ページ)。
このストレスへの耐性もまた、「どのように育てられたか」が影響します。ラットの新生児と母親を調べた研究では、母親ラットが生後12時間以内に子どもをどれだけなめ、毛づくろいしてやったかがストレスに反応する脳内化学物質に永続的な影響を与えるとの報告があります。
母親にたっぷりなめられた(かわいがられた)子ラットは、そうでない子ラットよりも勇敢で、ストレスを受けてもストレスホルモンの分泌量が少なく、回復も早いというのです(『身体はトラウマを記録する 脳・心・体のつながりと回復のための手法』ベッセル・ウ゛ァンデア・コーク/柴田裕之訳・紀伊國屋書店 254ページ)。
子どもは親の所有物ではない
みっつめは「子どもは親の所有物」との考えを改めることです。
日本では「しつけとしての体罰容認派」の親が多数であることは、すでに書きました(野田市小学4年生虐待死事件について考える(1))。つまり、「親は子どもをどのように扱ってもよい」と思っているおとなが大勢いるということです。
親の思いや都合を優先させ、子どもに何かを教え込もうとか、親の期待を押しつけようとすることを止め、子どもは自分とは違う、ひとりの人間であるという意識をしっかりと持つべきです。
たとえ社会で容認された行為であっても、それが子どもの思いや願いを無視した関わりであるならば、すべて虐待と地続きであると認識して子どもと向き合わない限り、虐待という悲劇はけっして止まないでしょう。