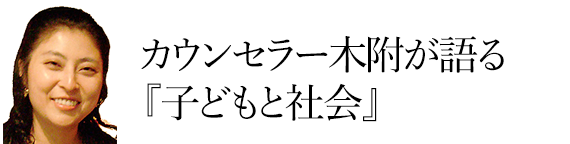児童相談所は子どもを守る最後の砦か(6/8)
大前提として、虐待のケースが後を絶たないことは否定しません。たくさんのケースを抱えて走り回る児相職員の方がいるのも知っています。繰り返しになりますが、何よりもこの国の福祉行政の貧しさが大問題だということも分かっています。
しかしそれでも、先のブログで紹介した女子高校生の声などを聴くと、「職員の対応も見直すべき点があったのではないか」と思うことがあります。
拘置所で母親が語ったこと
たとえば今年の夏、2013年4月に横浜市の雑木林で白骨遺体となって見つかった女の子の母親が拘置所で記者に語った話の記事(『朝日新聞』2014年7月29日)を読みました。
記事では、児童相談所の職員ふたりが訪問したときの様子や母親の心境をこう記していました。
「『最初から疑ってきた』。母子の服装や室内を見てメモを取る職員に被告(母親)は反発を覚えたという。
さらに態度を硬化させたのが、自身の生い立ちに質問が集中したことだった。『虐待を受けたことがないか、やたらと聞かれた』。虐待を受けた人は我が子を虐待することがあるーー後にそう聞いたが、触れられたくない過去を初対面で聞かれて不信感を持った。『でたらめばかり答えた』」
女の子が亡くなったのは、この9日後でした。
虐待親に寄り添う視点が必要
そもそも初動が遅すぎた、という問題があるでしょう。すでに訪問したときは、緊急避難としての危機介入をすべきときに来ていたという見方もできます。
そうしたタイミングを見逃さず、適切に対応するには、経験や勘、何より、「まず虐待せざるを得ない親の側に寄り添ってものごとを見る」視点が欠かせません。
この母親の証言を読む限り、そうした視点を職員は持っていなかったのではないかと思えてしまいます。(続く…)