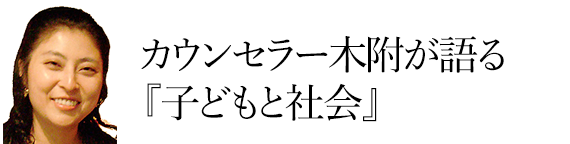さとり世代(7/10)
私が実際に会った子どもたちも同じでした。
たとえば、私が編集・執筆に関わった児童養護施設で暮らす子どもたちの声を集めた『子どもが語る施設の暮らし』(明石書店)という本の取材で出会った子どもたちもそうです。
90年代はじめくらいまでに出会った子たちは、施設での生活に不満を述べ、自らをこんな境遇に置いたおとなへの憤りを語ってくれました。その激しい怒りの矛先は、ときにインタビュアーである私に向けられ、私の中にも強いネガティブな感情を呼び起こすほどでした。
ところが、90年代後半、とくに2000年に入ると事情が変わってきます。同じように児童養護施設で暮らすこどもたちに話を聞いたにもかかわらず、子どもたちは、言葉少なに「べつに不満はない」と言い、「だって、仕方ないじゃん」と、冷めた目で私を見つめていました。
何を聞いても「べつに」「フツー」「流すだけ」と答えられてしまうので、インタビュアーとして、「たとえばこういうことに不満はないの?」「こんなおとなのことをどう思う?」と、焦りながら質問をした思い出があります。
怒りもいらだちもない
私がこうした子どもたちの変化を意識しはじめたのはちょうど2000年でした。
1997年に起きた神戸小学生殺傷事件以来、その加害者だったA少年と同年代の子どもたちによる事件が相次ぎ、「キレる17歳」が話題になっていた頃です。
当時、「キレる17歳」に共感を覚える同世代は少なくありませんでした。そんなひとりである17歳(当時)の少女が、こう言ったのです。
「こうやってずーっと競争させられて、周りを見ながら生きて、そうしたら『ほっと出来るのなんて、定年退職してからじゃん』って思ったら、なんか嫌になっちゃったよ。社会が変わるっていうか、変えられることなんかあるのかな?」
そこには、世の中を変えていこうという思いや、定年するまでホッとできない社会への疑問はありませんでした。
彼女にとって、今の世の中は「絶対に変わらないもの」で、「その中でいかに生き延びるのか」が大事でした。
当然、怒りも、いらだちも感じられません。(続く…)