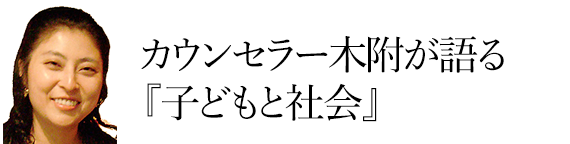感情を失った時代(6/10)
精神分析の権威として知られる精神科医の小此木啓吾氏は、1979年に出版した『対象喪失 悲しむということ』(中公新書)の「まえがき」で、「今日、悲しみを知らない世代が誕生している」と、次のように記しています。
「死、病気、退職、受験浪人から失恋、親離れ、子離れ、老いにいたるまで、あらゆる人生の局面で、対象喪失は、大規模におこっているのに、人びとは、悲しみなしにその経験を通り抜けていく。対象喪失経験は、メカニックに物的に処理されてゆく。対象を失った人びとは、悲しむことを知らないために、いたずらに困惑し、不安におびえ、絶望にうちひしがれ、ひいては自己自身までも喪失してしまう」(同書iページ)
自己や感情まで喪失
小此木氏の本を読み、今回の体罰事件を振り返ると、小此木氏が同書を記してからすでに30年が経過する中で、人びとは本当に自己を喪失し、自己を形成するための感情まで失ってしまったかのように見えます。
目の前で子どもが叩かれていても「それは勝つために必要なこと」と見なかった振りをし、「辛いよ」と声を上げても「がんばれ!」と励ます。そして、死ぬほどに追い詰められていても「もう嫌だ」と言わせない社会。
「感じることを止め、求められた務めを果たすこと」が、何よりも大切とされる・・・そんな感情を失った世代が築いた社会に、私たちは生きています。
あらゆる場で「感情労働」が求められる
そして感情を失った世の中だからこそ、今や逆に、あらゆる場で“求められる適切な感情”を演出する「感情労働」が求められます。
「感情労働」という概念は、ホックシールド氏の調査研究『管理される心 感情が商品になるとき』によって知られるようになったものです。
最近、エッセイストの岸本裕紀子氏は『感情労働シンドローム 体より、気持ちが疲れていませんか?』(PHP新書)という書を著し、その中で「仕事をするなかで、苦痛を感じたり、怒りをかきたてられたり、虚しさにとらわれたり、違和感を覚えたり、不安感が頭から離れなかったりしても、そういった自分の感情をうまくコントロールして、感じよく接し、相手のプラスの感情を引き出すようにする」(3ページ)ことが感情労働であると、営業職という身近な例を挙げてこう説明しています。
「新規開拓のため連日、足を棒にして何十軒と訪問しても、一件も契約が取れない。そうしたなか、丁寧に説明している途中で、バタンとドアを閉められたとします。『いくらなんでも失礼だろう』というショックや怒り、『はたしてこの商品は相手の役に立つのか』という疑問、『自分はいつまで不毛な戦いのようなこの仕事をつづけるのだろう』という虚しさや不安。
そういった感情を抑えて、前向きに、さわやかに次の訪問先に向かう・・・。」(4ページ)(続く…)