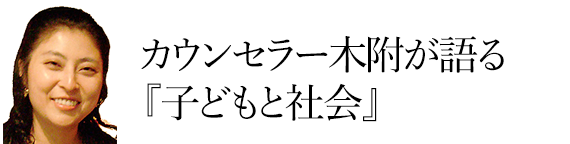歴史は心的外傷を繰り返し忘れてきた(2/8)
「どんな障害が待っているのか?」と、気になる方はぜひ映画を観ていただけたら、と思います。
ここでは私がなぜ映画『少年と自転車』に興味を持ったかをお話します。
それは、脚本と監督を手がけたジャン・ピエール氏とリュック・ダルデンヌ氏の記者会見の模様を偶然、テレビで見たからです。
映画制作のきっかけ
たまたまつけた番組で、チラッと見ただけですので正確な文言ではありませんが、兄弟であるふたりの監督は、『少年と自転車』制作のきっかけについて次のような趣旨のことを話していました。
「以前、来日したとき、ある弁護士から児童養護施設に預けられた子どもの話を聞きました。その子は、『迎えに来る』と約束した父親を屋根に乗ってずっと待っていた。でも、父親が迎えに来ることは無く、その子はやがて父親を待つことを止め、暴力の世界へと入っていったのです。『親に捨てられる』というこの上なく大きな暴力を振るわれた子が、暴力を振るう人間になるのは当たり前なことですし、父親のような存在である年上の非行少年に『認められたい』という気持ちも分かります。でも、その子の生い立ちに興味はありません。『どうしたら暴力の連鎖を止められるのか』を考えたのです」
映画のダイジェスト版が流れ、監督の上記のような発言を聴いたテレビのコメンテーターらは、「深いですね」と、口々に感心したようにつぶやいていました。
忘れっぽいのはなぜ?
だけど不思議に思うのです。
「映画の話」であれば、「暴力を受けた子どもが暴力を振るう人間になること」を抵抗なく受け止められるのに、現実の少年事件に対しては、どうしてそう思えなくなってしまうのでしょうか。
「映画の話」であれば、「暴力を止められるのは、その暴力を封じ込めるための暴力などではなく、暴力を振るわざるを得ないその子の悲しみに共感し、その存在を受け止め、常に寄り添ってくれる“だれか”なのだ」と、すんなりと入っていくのに、現実の非行少年に対しては厳罰化によって対処しようとするのでしょうか。
現実の世界では、親に捨てられたり、親に存在を無視されるという心的外傷ともなる仕打ちを受けた子どもに対して、その子の辛さや切なさに寄り添うのではなく、「頼る人間はいないのだから、少しでも早く自分の足で立て!」と尻を叩くのでしょうか。
感動した映画を現実の世界に当てはめられないほど、なぜに私たちは忘れっぽいのでしょうか?(続く…)