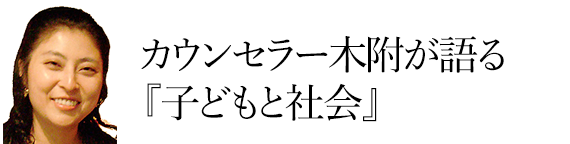家族って?(3/6)
当時、私は月に数回ほど東京の北東部にあるキリスト教会が行っていたホームレス支援ボランティアのお手伝いをしていました。
週末には公園でおにぎりやお味噌汁を配り、ウィークデーの夜には川沿いのダンボールハウスやテントを回り、そこに暮らす方の体調確認などをしていたのです。
ホームレスの方々の中には、何度か顔をあわせるうちに自らの過去や思い出話をしてくれる方もいらっしゃいました。
もともとは冬の時期だけ出稼ぎに来ていた東北出身の人、「いなかでコツコツ働くよりも」と、日銭の稼げた時代に東京まで流れて来た人、50代を過ぎて日雇いの現場が無くなってしまった人、体調を壊して働けなくなった人・・・いろいろな境遇の人がいました。
===
天涯孤独の人はめったにいなかった
でも、天涯孤独という人はめったにいませんでした。
「郷里には弟夫婦がいて・・・」
「娘とはもう10年以上も会っていない・・・」
「親もいい年だから心配だ・・・」
――そんな話が、チラホラと出てくるのです。
「気になっているなら連絡を取ってみたらどうですか?」
私がそう言うと、「そんなことできるわけがない。こんな姿を見せられるわけないじゃないか!」と、みな頑なに拒みました。
中でもいちばん私の胸を打ったのは、川の向こう岸を指し、笑いながら話してくれたおじさんです。おじさんは、こう言ったのです。
「俺の実家はね、この橋のすぐ向こう側にあるんだ。両親は死んで、今は弟が家を継いでいる。まさか俺がこんなところでテント暮らしをしているとは思ってもいないだろうね」
にじむ切なさ
寂しそうに笑うおじさんの顔には、「どうにか一旗揚げたら」「故郷に錦を飾るまでは」「妻や子にいい生活をさせてあげられるようになるまでは」・・・そんなふうに頑張り続けて、ここまで来てしまった多くの人々の哀しみが重なって見えました。
「もう少し」「あともう少し」・・・そう思っているうちに、流れて行ってしまった長い年月。意地を張り、「いつかきっと」と思っているうちに、深まってしまった肉親との溝。
「今さら帰れない」と話す彼らの横顔には、夫婦だからこそ、親子だからこそ、肉親だからこそ、素直に弱みを見せることができなかった、そのままの自分を出すことができなかった切なさがにじんでいました。(続く…)