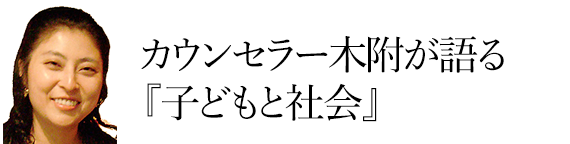排除の論理と子どもの気持ち(3)
 そんな「おとな都合」の社会から最も排除されがちなのは、「子ども」です。
そんな「おとな都合」の社会から最も排除されがちなのは、「子ども」です。
自分一人では移動もままならず、何一つひとりではできない社会的弱者を体験させてもらうことになって、「ああ、子どものときってこうだった」と思い出すことが何回もありました。
おとなに大切なものを壊されて抗議すれば「だれが買ってあげたものなのか」と言われ、おとなたちが宴たけなわにお酒を楽しんでいるときに「早く帰りたい」と言えば「わがままだ」と言われたこと。
ありありと甦ってきた
「ああしたい」「こうしたい」「これは嫌」と訴えても、「だったら自分でどうにかしなさい」と言われ、黙るしかなかった自分。
楽しく遊んでいても「もう時間なんだから」と引きずられて帰るしか無く、お腹が空いてもじっーと待つしかなかった自分。
いつもいつも「どこかおかしい」と思いながらも、返す言葉を持たなかった幼い日の自分のことが、骨折を経験し、ありありと甦ってきました。
「子どもの気持ち」を改めて実感
自分だけで何かができないということ。自分で自分の面倒をみられないということ。自分の思うように動けないこと。それはとっても辛いことです。
頼る相手が忙しそうにしていたり、少しでも迷惑なそぶりを見せれば、何も言えなくなってしまいます。
そんな何もできない、だれかに頼らざるを得ない存在が、自分のことを「情けない」と思うことなく、「ここにいていいんだ」、「自分の思いは当然なんだ」と感じられるようになるためには、身近なだれかがいつもでその存在に関心を持ち、何か訴えれば顔を向け、その欲求を満たしてくれることが必要です。
だから子どもは、いつもでもおとなに愛されたくて、おとなの顔色をうかがってしまいます。
そんな「子どもの気持ち」を改めて知ることができた、貴重な骨折体験でした。