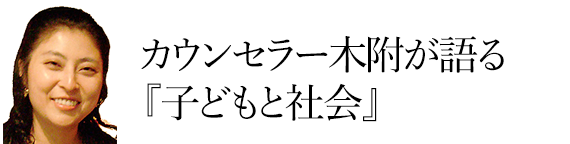遺族を訴訟に追い込んだ大川小学校事故検証委員会(4/7)
何しろ検証委員会は、せっかく集めた証言までも「プライバシー保護」を盾に、どんな立場の、どんな人物が証言したものかをぼやかしてしまいました。
そして、相反する証言をただ並べ立て、羅列しました。
「山への避難を訴えたり、泣き出したり、嘔吐する子どもがいた」と書いたと思えば、その一方で「遊び始めたり、ゲームや漫画など日常的な会話をしていた」と記すなどして、検証という行為を放棄しました。
こうして検証委員会は、何一つ新しい事実を提示できなかっただけでなく、遺族の方々が事故直後から集め続け、積み上げてきていた事実を曖昧にしてしまいました。
そうして「津波予想浸水域に入っていなかったから危機意識が薄かった」「裏山は危険で登れないと思っていた」など、「子どもたちが命を落としたのは仕方なかった」と言わんばかりの最終報告をまとめたのです。
震災後の大川小学校校舎
遺族の方々は、「学校にいるから、先生と一緒にいるんだから、絶対に大丈夫と信じていた」と口をそろえます。
私がお会いした遺族の方々も、「大きな揺れの後、時計を見たら、まだ学校にいる時間だったから『ああ、うちの子は大丈夫』と、まるで心配しなかった」「先生がちゃんと避難させてくれているはずだから、明日になれば必ず会えると信じていた」と、語っておられました。
そうした胸を打つ数々のご意見のなかでも、ひときわ私の心に響いた発言がありました。小学校6年生の長男を亡くし、検証委員会をずっと傍聴し続けてきたお母さんが語った言葉です。
「『たったひとつだけでも、先生が子どもたちを守るためにしてくれたことがあれば』と、検証の行方を見守って来ました。でも、検証を重ねて分かったのは、助けるどころか、逃げようとした子までその場に止めていたということでした」
保護者の切なる願い
子どもを亡くし、市の教育委員会からは不誠実極まりない対応を受け、核心に迫ろうとしない検証委員会・・・。それらと対峙するだけでも、計り知れないほど辛い思いをされてきたことでしょう。
でも、それでも、「どうにかして先生を信用したい」「『先生もあなたを守るためにがんばってくれたんだよ』と子どもに伝えたいと」という切なる願いが、このお母さんの言葉から、ほとばしるように感じられました。(続く…)